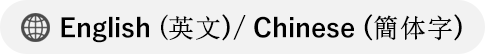『戦後中国の憲政実施と言論の自由 1945-49』(東京大学出版会、2004年8月)
主要目次

税込7140円/本体6800円
ISBN 4-13-026123-1
- 序 章
- 第1部 憲政実施と言論政策
第1章 抗戦末期の言論政策/第2章 戦後の文化政策機関の変遷――憲政実施と党・国家体制/第3章 戦後国民政府の言論政策 - 第2部 戦後言論界の実態
第4章 戦後言論界の復員情況/第5章 戦後自由主義経済と新聞・雑誌の商業化 - 第3部 戦後思想界の憲政批判
第6章 雑誌『観察』の憲政批判/第7章 憲政実施をめぐる文化論争 - 終 章
- 史料・文献一覧
内容紹介
政治の民主化という視点から近現代中国史を見通したとき,戦後の「憲政」実施期はきわめて大きな意味を有している.本書は,戦後の「憲政」と1940年代の内外情勢との関連性を「言論の自由」の視角から読み解き,現代中国を射程に入れながら新たな戦後中国史像を提示していく.東京大学出版会刊行助成図書.
Summary
<Constitutionalism and Freedom of Speech in China during the Civil War period, 1945-49
The more recent history of China in the last two decades has gone through great changes as a result of the transformation of its political line and changes in the socio-economic paradigm. The most significant change has been the demise of the “Revolution-focused idea” which had previously been the most glorious feature of the history of the Chinese Communist Party. As a result, a fresh attempt has been made to develop a framework for the study of “the History of the Republic of China” in order to reassess its efforts to build a modern nation state. In addition, archives in China and Taiwan have been made public, which has allowed China to establish a favorable environment for experimental study. In these circumstances, this study attempts to provide a synthesis of the text through undertaking a study of the issue “Constitutional Democracy” during the National Government period (1928-49).
This study aims to review the results of previous studies which have placed exclusive emphasis on the dark side of post-war China whilst negating the post-war National Government (1945-49). In other words, it is my intention that this humble work may re-shape public perception of post-war China, which used to be undemocratic. I hope to achieve this by reflecting upon the constitutionalism enforced in 1947 from the standpoint of freedom of speech.
The reason why I focus on freedom of speech in this paper is not because I wish to present the ideas of some jurists who contend that freedom of speech is the barometer of democracy, but rather because I would like to take a direct look at the historical scholars in China during 1930s-40s as follows:(1) Those intellectuals who were constantly demanding the “democratization of politics” when the intellectuals who acted in concert with the People’s Political Council or Chinese Democracy League maintained freedom of speech, (2) Influenced by the “Constitutional movement” derived from it, the National Government was relaxing its policy towards the press whilst receiving most of the opinions of the Commission for the Inauguration of Constitutionalism, (3) A reorganization of the central party-government relationship is taking place; for example, the Propaganda League(party) and the Civil Ministry(government) are in conflict with each other over the issue of the registration and censorship of newspapers, magazines and books which are part of the cultural policy, resulting in the need for the reorganization of the Propaganda League.
However, it is not possible to analyze liberalization and democratization solely from the perspective of government system and policy. It goes without saying that it is also crucial to analyze its actual situation. In the case of the main body, it is important to resolve the problem with the ideology of the policy using various data in order to see how they have been reflected in the world of the press. Moreover, the press is a profit-motivated institution, so as long as the democratization of politics is a dependent factor of the maturity of the market economy, the actual situation needs to be analyzed based on the starting point of commercialization and marketing.
In addition, in the case of the main body, it is crucial to adopt the criticism of constitutionalism by the press. Thus it is necessary to review the actual situation of the press in terms of quality as well as date. This means that it is also very useful to show to what degree the then world of thought was allowed to criticize the government, as well as analyzing the nature of newspaper and magazine companies and regional variance. Besides, since liberalization and democratization are based on Western (American) values and systems, conflict exists between the recipient and such ideas. As a result, analysis of cultural clashes within the mind of the recipient allows one to evaluate to what extent the cultural base of the constitutional system guarantees freedom of speech institutionally.
In studying constitutionalism and freedom of speech in China during the civil war period (1945-49) through this book, Part 1 will discuss trends in internal situations and the evolutionary development of the system and policies of the government based on the domestic and foreign political circumstances of the time (Section 1- 3). Part 2 deals with an analysis of the restoration and with the problems of the commercialization and marketing of newspapers and magazines (Section 4-5). Finally, Part 3 will deal with an analysis of the criticism of the current constitutionalism (Section 6) and the criticism by the press of constitutionalism based on the cultural perspective (Section 7).
In the conclusion drawn from the analysis presented in each Section, it can be seen that a Chinese movement existed with the aim of deactivating wartime control under given trends of international liberalization and democratization. Such real conditions prompted the transformation of post-war China to constitutionalism and the transformation process does not rule out the possibility of separating the Party from the government. Although the vitality of the press was clearly evident for some time during the post-war period, many initiatives and projects suffered setbacks for a variety of reasons --tensions in international politics, the collapse of the government’s policy towards a liberal economy, or the lack of a cultural foundation which is sufficiently strong to establish constitutionalism -- and such a positive picture has rarely been presented thus far. My humble work attempts to re-paint the existing picture of post-war China, which presents solely the dark side of China, and to make it clear that the post-war national government was attempting post-war reconstruction whilst taking account of domestic and international politics which in the 1940s were demanding liberalism and democratization. It also attempts to show that, against the harsh backdrop of the civil war and the US-Russian Cold War, the influence and thinking of the press were ? albeit temporarily - showing signs of rehabilitation and growth.
As such, reconstruction of the perception of post-war China should be able to give us true access to the history of the appropriate period and the “revolution-focused historic view”. In addition, such access will also allow an unraveling and interpretation of the ideology of the political system and democratization of modern Taiwan, or of the evolutionary process reaching the Anti-Rightist Campaign in mainland China, as well as of the theory of political system reform, together with the cultural and human rights issues which have been emerging since the 1980s from a historical point of view.
お礼
お便りでコメント・ご批判くださった先生方には大変感謝しております。また、ご高論において引用してくださった先生方、学会誌・研究会などで貴重なコメントをお寄せくださった方々にも、改めてお礼申し上げます。
- 村田ゼミ合宿(於箱根、2004年9月)
- H氏ブログ(2004年10月5日)
- 「情報・メディア法」・「東アジア法」の「2004年学界回顧」(『法律時報』、2004年12月号)
- 三谷博(東京大学)「公論形成―非西洋社会における民主化の経験と可能性」(同編『東アジアの公論形成』東京大学出版会、2004年12月)
- 張生先生(南京大学)との交流会(於南京大学、2004年12月)
- 水羽信男(広島大学)「中華民国後半期(1928-1949)政治史研究総述―日本中国近代史研究的成果与今後的課題―」(『地域文化研究(広島大学総合科学部紀要Ⅰ)』30巻、2004年)
- 水羽信男(広島大学)「日本的近代城市史研究」(『歴史研究』2004年6号)
など。
<拙著への書評
- 水羽信男(広島大学)「書評報告」(於中国現代史研究会、2005年1月)
- 鈴木賢(北海道大学)「書評」(『中国研究月報』No.687、2005年5月)
- 山本真(筑波大学)「書評」(『歴史評論』663号、2005年7月)
- 平野正(大東文化大学)「書評」(『史学雑誌』114編7号、2005年7月)
- 林幸司(一橋大学・院)「書評」(『現代中国研究』17号、2005年9月)
←私の怠惰で回答を掲載し忘れておりましたが、ご本人にはお礼を申し上げておきました。改めて御礼申し上げます。 - 松田康博(防衛研究所)「書評」(『歴史学研究』No.817、2006年8月)
- 水羽信男(広島大学)「書評」(『史学研究』253号、2006年8月)
訂正
お詫び申し上げます
| ページ数 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|
| 12頁/写真1 | 1945年 | 1946年 |
| 58頁/注61 | 「・・・世界平和」 | 「・・・世界和平」 |
| 87頁/上から2行目 14頁/上から8行目 |
総動員法 | 総動員令 *戦後に総動員法は政権内部で廃止が検討されていたが、結局、廃止は見送られたようである(ただし、この間、総動員体制は発動されていなかったと解釈されている)。1947年7月の総動員令により、再び総動員体制へと動き出すことになった。したがって、文意に変更はない。 |
| 90頁/下から4行目 | 韓特培 | 韓徳培 |
| 108頁/注9 | 「・・・官制・・・」 | 「・・・管制・・・」 |
| 182頁/表6-4/下から15段目(左) | 前四川大学校長 台湾 | 前四川大学校長 大陸 |
| 182頁/表6-4/下から5段目(左) | 楊緯 | 楊絳 |
| 184頁/上から6行目 | 制憲国民大会に参加した民社党指導者 | 民社党の制憲国民大会への参加を容認した |
| 221頁/下から10行目 | 百家斉放 | 百花斉放 |
| 234頁/最終行 | 『抗日戦争と民主運動』創士社 | 『抗日戦争と民衆運動』創土社 |
追加情報
| ページ数 | 関連箇所 | 追加情報 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7頁・93頁・95頁など | 報道・新聞自由小委員会 | 情報および報道の自由小委員会 | 現在は後者の訳語が定着しているようです。 |
| 82頁/注43 | 馬星野論文から引用したエディター・アンド・パブリッシャー誌の中国評価に関する原文。ニューヨーク公立図書館で入手。 | The last vestiges of official censorship --except in the Russian-occupied zones-- were lifted March 8, and chinese officials have gone for to make good on some of the promises of press freedom they voiced to the ASNE (注: American Society of Newspaper Editor) Committe a year ago. Freedom of access to sources is still short of anticipated goals. No one expect a designated correspondent of the government-sponsered Central News Agency was permitted to cover the Central Exective Committe of the Kuomintang, and even that a correspondent was ordered to withhold certain information.…… | 検閲解除の動向を評価しつつ、その不十分さにも言及。ただし、報道の「完全な」自由を求めるアメリカの立場は、イギリス・フランスとも温度差があり、中国に限らず他国への批判が厳しくなりがちなことにも注意すべきか(?)。 |
| 87頁など | 総統府立法院 | 民選立法院(山本真氏)と表記すべきだったかもしれない。 | 史料用語ではありませんが、制度史辞典から借用しました。 |
| 93頁/注79(座談会) 102頁/中段(第19号) 219頁/中段(座談会)など |
立法院における修正「出版法」審議過程と国連報道自由会議 | 国連報道自由会議では、米ソ対立のみならず、先進国と発展途上国との対立もあった。中国は自国のメディア産業を保護するため、アジア・ラテンアメリカ諸国とともに、英米中心の報道自由論を「時には」牽制し(国連報道自由会議決議第19号は中国が提案した)、それが中国国内の統制再強化へとつながった。つまり、統制再強化論には国内産業の保護という視点もあったのである。 | 2005年8月の南京国際シンポジウム提出ペーパー「国民党的新聞自由論与民権思想――従20世紀40年代国際情勢的角度来分析」で検討。 |
| 146頁/注17 | (右の情報を追加) | 葉再生『中国近現代出版通史(4巻)』(華文出版社、2002年)1036頁 | ―――― |
拙著への書評
水羽信男(広島大学)「書評報告」(於中国現代史研究会、2005年1月)
2005.2.4作成、2005.2.9/2005.6.6改訂
水羽先生は、私の研究テーマに最も近い研究者。それだけに、厳しいご批判をたくさんいただきました。
しかし同時に、この時期の政治史・思想史を扱うことの厳しさを最もよくご存知の研究者。そして、新しい方向性を絶えず模索されている研究者。正当に評価してくださったことには、大変感謝しております。
主要な論点
| ポイント① | 香港言論界への高い評価について |
|---|---|
| コメント要約 | 銭理群『一九四八:天地玄黄』(山東教育出版社、1998年)は、香港における左派系言論の非(反)リベラリズム性を指摘し、延安整風から戦後香港へと連なる左派系の言論活動を1950年代の思想改造へと人的にも思想的にも連続している、と理解している。 また、仮に香港の役割を高く評価するとしたら、自由主義的な「言論空間の縮小」という観点から戦後香港はどのように位置づけられるのか。 |
| 私見 | 戦後香港には、左傾的思想のみならず、自由主義思想も生息しうる空間があったと考える。確かにイギリス香港政庁は共産主義に対する取締りを1948年後半以降強化していくが、依然として自由主義思想はそれなりに許容されていたと言える。だからこそ、国民政府統治地区の言論空間が狭められてく中で、戦後香港は一定の役割を果たせたと思う。 ただし、香港政庁が共産主義に対する取締りを強化し、それ故に左派系人士が東北へと移動した、との結論はやや表面的だったかもしれない。つまり、共産党側の知識人戦略が香港から東北への流れを生み出した、とも考えられる。この点を汲み取れれば、東北問題に特に言及せずとも、内戦期における東北の意味をしっかりと伝えられたかもしれない。 |
| 補足 | 関連するコメントは参加者の方からもいただきました。議論を通じて、その後の人民共和国と香港との関係を見据えつつ、1945から49年の香港を位置づける必要がありそうです。 <水羽先生より(2005.3.25)> 香港には自由な「言論空間」が存在した。が、それゆえにその地で自由に活動した左派系の知識人の言論活動が、上海・平津地区の「中間路線」論を厳しく批判しえた。そのことの功罪をどう考えるか。従来は『光明報』などを「民主」的と高く評価する傾向が強かったように感じるが……。 |
| ポイント② | 内戦期にもかかわらず、東北問題に言及がないことについて |
|---|---|
| コメント要約 | 東北問題にもっと言及すべきではなかったか。 |
| 私見 | 戦後の東北は、国共対立・米ソ冷戦の縮図。もっと積極的に取り上げるべきだったかもしれない。 しかし、東北問題を敢えて強調しなかった理由は、以下の三点に由る。 ①档案を見る限り、当時の言論政策担当者は東北問題を特に重視していたわけではない。むしろ、東北を除く旧日本軍占領地域によりウェイトを置いていた(2005年1月のソウル会議でも少し話題になっていた)。 ②東北問題に限定して冷戦構造や国共関係を紐解くよりも、全体の記述の中でそれらを分析したかった。 ③私の主眼は地域の差異を分析することにあるのではなく、国民政府統治地区全体の動向を浮き彫りにすることにあった。もし②の意図が成功していれば、拙著における東北分析の意味は限りなく小さくなる。 |
| 補足 | ただし、東北を個別具体例として扱っておけば、反米反国民党ナショナリズムをより強調できたのではないかとの反省は残る(←この点は水羽先生からもご指摘をうけた)。 |
| ポイント③ | 1949年革命の理解について |
|---|---|
| コメント要約 | 憲政失敗を考えるにあたって、経済政策や地政学的見地からのナショナリズム、あるいは国民党・国民政府に内在していた要因をどう考えればいいのか。また、失敗の一因である「文化的基盤」とは如何なるものか。 |
| 私見 | 近代化論や従属論の陥穽から逃れるためにも、失敗の要因を複合的に捉える必要がある。もちろん経済的要因を否定するつもりはなく、拙著第五章でも触れている。また、ナショナリズムの影響の深刻さについても、「政策過程」の分析で適宜言及したつもりであり、その要因を排除しているわけではない。さらに、私見によれば、政治制度を根付かせる、もしくは政治文化を形成する各国固有の「目にみえない基盤」も考えなければならないと感じている。ただし、そうした基盤は漠然としているだけに、「文化的基盤」の意味を明確に説明できいているわけではない。拙著の「文化的基盤」とは、序章でも触れとおり、制度が定着した際の「文化の平衡状態」(平野健一郎『国際文化論』東京大学出版会、2000年)を指すものとご理解願いたい。 |
| 補足 | 1945-49年の文化論争は、抗戦以前のそれと改革開放以後のそれとを媒介するもの、と考えている。 |
| ポイント④ | 自由主義的傾向が弱まった理由について |
|---|---|
| コメント要約 | アメリカも権力内部で主流になりえなかったと判断(『中国白書』)しているが、それはアメリカでの反共主義の高まりとともに、アメリカに対する自由主義的ポーズをとる必要が無くなったからか。あるいは、派閥闘争などを背景に自由主義的な政策の幅が狭まったからなのか。 |
| 私見 | 77-80頁で指摘したとおりであるが、派閥闘争を背景に政策の幅が狭まっていったことも一因かもしれない。ただし、アメリカの自由の中身がどうであれ、戦後の五大国の一員として、最後まで自由主義を放棄しなかった点は確認されるべきであると考える。 |
| 補足 | 拙著はリベラリズムそのものを分析対象としているわけではないが(5頁)、もう少し「国家・民族」(ナショナリズム)と「自由」の関係を説明したほうがよかったかもしれない。 これまでの研究は、国権に劣位する、もしくは「公」へと回収される人権観をしばしば強調しており、拙著がこの点を前提にしていることは、52頁の引用箇所や終章の国権・人権論からも読み取っていただけるとは思う。ただし、こうした中国特有の人権意識を指摘する研究者のなかにも「中華民国憲法」の諸権利を比較的高く評価することがあり(アンドリューネイサン「中国憲法における政治的権利」、R.ランドル・エドワーズほか著『中国の人権』有信堂、1990年)、人権をより重視するような方向性も見出せるのかもしれない。 |
| ポイント⑤ | 1949年前後の連続と不連続について |
|---|---|
| コメント要約 | 戦時期の統制政策と戦後の自由主義政策をどう統一的に解釈するのか。自由と統制の関係を煮詰めていけば一つの像を描けるのか。 |
| 私見 | 終章でも指摘したが、これは最も大切な論点であり、今後深めなければならない課題である。 自由は一定の秩序において実現されるのであり、「自由と民主主義の相克」を指摘するまでもなく、無制限の自由など有り得ない。そこには当然、戦時期の統制論の影響も残っているだろう。しかし、そうした自由の性質を逆手にとって統制論へと全てを収斂させては、1950年代の台湾政治史や反右派闘争、もしくは現代中国・現代台湾の動向を見通せないのではないか。どちらが正しいか間違っているかの問題ではなく、実証かつ理論的に深めていかなければならない課題である。 |
| 補足 | その他の重要な論点③④も参照。 <水羽先生より(2005.3.25)> 1949年革命に関しては、書評会でのレジュメでも示したように、本書の指摘は踏まえているつもり。久保・奥村両氏の研究を素材にあげたうえで確認したかったのが、「文化的基盤」の意味。というのも、国民政府・国民党史研究に即していえば、あれかこれかではなく、総体として見たとき、その時代のイメージを如何に描くべきか、という点が水羽の最大の関心事だから。 ……工業化の問題などと異なり、自由主義の問題は、「エセ自由主義」との批判や、本質的ではない一時的な政策のブレなどといった形での理解によって、所詮、国民党の自由主義とは反革命的なものとの批判が起り得るのではないか、という危惧もある。 |
その他の重要な論点
- 青年党・民社党を再分析する必要性。
- 民主憲政と司法制度。
- 新県制以来の地方制度をどのように捉えるべきか。→ポイント⑤に直結する極めて重要な論点。
- 自由・民主主義と社会統合(or自由と民主主義のジレンマor自由主義の整理)→ポイント⑤に直結する極めて重要な論点。*拙著の目的は、中国近現代のリベラリズムを定義することではない。
- 国民党・国民政府の性格を全体としてどのように理解していくのか(水羽先生のコメント)。
- 政権内部のリベラリズムと政権外部のリベラリズムとの関係は?(→政治史研究と思想史研究→次の問題へ)
- 制度・国家と思想・概念の連環→これまでの思想史研究は「制度・国家→思想・概念化」の視点があまりにも弱すぎた。両方向で考えなければならない。
鈴木賢(北海道大学)「書評」(『中国研究月報』No.687、2005年5月)
2005.6.6作成
鈴木賢先生、お忙しい中、拙著を書評してくださり、有難うございました。法学をご専門とされている先生からも「反動的で反面教師としてしか省みる価値のない国民党統治という先入観を覆すに足る事実を掘り起こし」た(36頁)と評価していただけたことは、励みになります。また、現代中国との比較において民国末期の言論空間を相対化してくださったこと(36-37頁)は、拙著の意味を歴史学において再確認してくださったように感じます。
主要な論点
| ポイント① | 1944年の戦時言論統制緩和政策とその実態(36頁) |
|---|---|
| 私見 | これまでの歴史・文学研究は、事前検閲と事後検閲の質的な違いについて、見落とすかもしくは軽視してきたように思われる。この両者の違いに注目した分析作業を的確に評価してくださったことに、まずお礼申し上げたい。 次に、この政策の結果についてであるが、事後検閲の認められた雑誌・図書については、自由な空間が少しずつ広がっていたと考えてよさそうである。なぜなら、検閲コードが緩められ、それまで扱えなかった一部のニュースを論評できるようになったからである。もちろん、国民党政権が政府批判の記事を事前に差し止めることは依然として続いていたが、その事実を知らせる行為自体――検閲箇所を空欄にしておくetc.――は認められるようになった。この点については、拙稿「戦時言論政策と内外情勢」(石島紀之・久保亨編『重慶国民政府史の研究』東京大学出版会、2004年)第4節で分析している。 |
| 補足 | 戦後を考察対象とする拙著においては、抗戦期の実態分析をあえて省略しました。 |
| ポイント② | 知識人による文化論争と民主憲政の「文化的基盤」(37-38頁) |
|---|---|
| 私見 | 「文化的基盤」を問うとき、「中国伝統文化のこの部分が民主憲政の理念と符合する」あるいは「摩擦を引き起こす」と一つ一つ具体的に分析していくことが最も望ましい説明方法である。したがって、この点に関するご批判は全面的に受け入れざるを得ないし、論旨にかかわる本質的なご批判として謙虚に受けとめざるを得ない(水羽先生のコメント③も参照)。 しかし、同時にご指摘くださっているように、この課題に「正面から切り込むことは容易」ではない(38頁)。そこで、正攻法の説明の仕方ではないが、「文化的基盤の不安定さ」を示す一つの事例として知識人の文化論争に注目した。なぜなら、知識人が伝統的素養を身につけているが故に、彼らの意見対立は西洋化と本土化との摩擦を(間接的にであれ)体現しているからである。 なお、法学界の「本土資源論」の代表的論客・蘇力の影響力については初耳であったが、私は「法の本土資源論」をめぐる論争も含めて「文化論ブーム」と形容しており(拙著220頁など)、法学界の東西文化論争をまったく視野に収めていない(38頁)わけではない。拙著での言葉足らずを反省している。 |
| 補足 | 博論審査会の前段階にあたるファイナル・コロキアムにおいて、この両者の関係について深く掘り下げたい、と回答したところ、別のテーマになり得るからよく考えるように言われました。政治と文化をめぐる問題は、いつか取り組んでみたいです。 |
| ポイント③ | 法秩序の不健全性について(38頁) |
|---|---|
| 私見 | この言葉が含意するのは二つである。 一つは、「法が文言に忠実には運用されず、実定法を離れて恣意的に適用される」(37頁)ことである。もう一つは、法の中身や政策的意図の原因や結果を議論する以前の末端統治体制の不備である。この視点は近年の民国史研究の成果でもある。 一部の地域において法の伝達経路自体に欠陥があれば、法の執行が阻害されることは明らかである。例えば、中央政府が統制強化の法令を発し、首都南京や主要都市においてそれが忠実に(あるいは恣意的に)実行されたとしても、一部の地域ではその法令自体が運用されず、結果的に統制が及ばないケースがある。 |
| 補足 | この点についても、やはり拙稿「戦時言論政策と内外情勢」(石島紀之・久保亨編『重慶国民政府史の研究』東京大学出版会、2004年)第4節で簡単に触れておきました。 |
| ポイント④ | 党報株式会社化と言論の自由について(38頁) |
|---|---|
| 私見 | この箇所で最も強調したかったことは、党報が株式会社化されなければならないほど、当時の言論界は活力があった、ということ(拙著160頁)。従来の中国近現代史研究(政治史・メディア史・思想史)において、この事実はほとんど置き去りにされてきた――管見の限り例外は曾虚白・水羽信男・張憲文[ほか編]の研究――。 しかし、拙著では明示していないが、党報の株式会社化は言論界を活性化させた一因だと考えられる。 たとえば、90年代の中国大陸におけるメディア史研究において(劉家林編著『中国新聞通史(下)』武漢大学出版社、1995年、349頁など)、株式会社化を前に『中央日報』が紙面の「雑誌化」に努め、「副刊」を重視していたことが指摘されている(拙著156頁も参照)。また、党報とはいえ、経営の自立化が政権との距離を少しずつ広げる可能性を秘めていたことも否定はできない。この点については、宣伝政策の全般的傾向を視野に入れつつ、人事・社論・経営の三側面から初歩的に考察している(拙稿「国民党政権と南京・重慶『中央日報』」中央大学人文科学研究所編『民国後期中国国民党政権の研究』中央大学出版部、2005年)。 もっとも株式会社化と関連づけた上記の説明は、他方で「株式会社化という形式面での変化以外の事情」(38頁)をも含んでいると理解できることから、その意味において、鈴木先生のご指摘は鋭い。 |
| 補足 | 蔡銘澤氏の研究を引用しつつ、株式会社化直後に経営基盤は強化されたと書きましたが(拙著160頁)、それが全ての党報で共通した現象ではなかったことも同時に指摘しています(拙著168頁)。こうした党報の経営難も言論空間縮小の一つの現象だと考えます。 |
山本真(筑波大学)「書評」(『歴史評論』663号、2005年7月)
2005.6.26作成、2005.8.24改訂
拙著を近年の新しい研究潮流のなかに位置づけてくださったことに、また、内政と国際情勢との相互規定性を解明した拙著の成果に注目してくださったことに、まずお礼申し上げます。評者の山本さんとは、研究の領域が異なり、中国近現代史に対する理解も完全に一致しているわけではありませんが、研究を支える「精神論」は共通しているようです。だからこそ、以心伝心する何かを言外に感じ取れたような気がします。もちろんご批判は真摯に受けとめますが、励みにもなりました。有難うございました。
主要な論点
| ポイント① | 国民党内自由主義派(孫科・王世杰ら)の政治思想の解明(103頁) |
|---|---|
| 私見 | 孫科・王世杰については、参考文献に列挙した高華論文・聞黎明論文・張国鈞論文が先駆的に解明しており、拙著においても大いに参照した。 ただし、「国民党内自由主義派」とでも呼ぶべきような彼らの政治思想は、充分には解明できていない。ここで「充分に」という理由は二つある。 第一の理由は、呉国楨・雷震らに代表されるように、のちに民主化をめぐって蒋介石と対立していく国民党内自由主義派の政治思想が「系統だって解明されていない」からである。これまで「CC派の一員=保守反動派」と理解されがちだった程滄波にしても、抗戦期には『中央日報』の経営自立化を模索し、戦後には「国連報道自由会議」において報道の自由化に賛成するなど、1950年代における彼のメディア自由論へと連なっていくような政治思想を大陸時代に展開していた。残念ながら、こうした党内の動向についても、「ほとんど注目されていない」。 第二の理由は、彼らの政治思想研究が派閥闘争研究となりがちで、彼らの本音がどこにあるのか理解しづらいからである。そして、中国近現代史におけるリベラリズム研究そのものが、経済史・社会史・文化史と比較して、それほど深化しておらず、彼らの「自由主義」を定義しにくいからである。今後は、政策決定過程時の利害対立(派閥闘争)と内外における情勢変化とを同時に把握できるような新しい方法論を創出し、中国近現代リベラリズムの一環として彼らの思想を位置づけなおさなければいけない。 これらの限界点は、もはや野ざらしにはできない。評者が暗示するように、1950年代の台湾政治史研究を深めていくためには、誰かが取り組まなければならない緊要の課題である。 |
| 補足 | 憲政実施協進会と国民参政会に対する専論も俟たれるところです。 |
| ポイント② | 戦後後期の政策過程分析について(103-104頁) |
|---|---|
| 私見 | ご指摘のような理由から、民選立法院における「出版法」改正議論(1948年7月-12月)をもっと緻密に分析すべきだった。そして、立法院を介した世論と政策決定過程の構造的分析をすすめるべきであった。(*台湾史研究会主催「第9回現代台湾学術討論会」報告ペーパー[同研究会編の学会誌に掲載予定]で分析してあります。) |
| 補足 | この数年のうちに、大陸・台湾の若手研究者を中心に、優れた立法院研究が生まれてくるのかもしれません。(日本では、金子肇氏・山本真氏の研究が先駆的。) 楽しみにしています。 |
| ポイント③ | 戦後の統制政策について(104頁) |
|---|---|
| 私見 | マクロな視点から戦後中国史を再考した拙著の立場は、理解していただけた。 ただし、拙著でも随所に指摘したとおり、戦後に各種の統制手段が完全に無くなったわけではない。その主要なものは登記制度であり、第四章第三節で分析したが、それ以外にも(1)紙の配給制度――1947年春に始まり幣制改革が破綻した1948年夏にストップ(2)郵便制度(3)特務による圧迫を考える必要がある。 私自身も最後までこだわったのが、この三点であった。(1)(2)(3)の視角から左派系メディアの活動実態を分析できればよかったが、史料の残り方に多くの問題があり、断念せざるを得なかった(拙著172-173頁のような記述になった理由)。そして、(1)~(3)を考えれば考えるほど、国民政府の「法治と非合法活動」の関係を再考する必要に迫られてくる。つまり、国民政府が法治を目ざしていたが故に、法の不備を逆手に取った共産党が効果的な反政府活動を展開でき、それに対抗するために、政府が(1)~(3)の手段を採用した、という「非合法活動後手論」の可能性である。事実、右派のレッテルを貼られ報道の自由化にも積極的であった元新華社記者戴煌氏は、「国民党は新聞法[注:出版法のこと]を制定したが、我々共産党はその弱み、そのスキにつけこみ、逆に我々の利用するところとなった。現在、我々は権力を掌握しているが、もし新聞法を作ったなら、下心のある人間に利用されることになりはしまいか。この法律がなければ、我々の立場は主導的でコントロールしたいようにコントロールできる。だから、やはり作らないほうがよい。」と毛沢東が発言した、と回想している(横澤泰夫訳『中国 報道と言論の自由』中国書店、2003年、56・58頁など)。 したがって、各種の統制政策を浮き彫りにする作業以前に、国民政府の「法治の在り方」を法制史・政治史・社会史の立場から、全面的に解明することが必要かもしれない。 |
| 補足 | 民国法制史の進展に期待しています。私も、著作権研究を通じて解明していければと考えています。 |
平野正(大東文化大学)「書評」(『史学雑誌』114編7号、2005年7月)
2005.8.30作成
先生には事前にお伝えしてございますが、この一ヶ月間、南京大学中華民国史研究センター客員研究員として在外研究をおこなっていました。お返事が遅れたこと、お詫び申し上げます。
平野先生、拙著に対する書評、有難うございました。私の苦労を一部認めてくださったことには、まずお礼申し上げなければなりません。しかしながら、世代間ギャップに起因するのかどうかは分かりませんが、やはり埋めがたい溝は残りました。
本来ならば、一つ一つに丁寧にお答えしなければなりません。たとえば、第三勢力などの在野の運動および世論についてですが――政策は場合によっては国内の在野の運動および世論とは切り離された形で、あるいはそれらに先行する形で決定されることもありますが、この点はもう少し分厚く分析してもよかったかもしれません――、「先生に満足していただけるほど重視」しているのかと聞かれれば、恐らくそうではありません。しかし、だからといって、決して軽視しているわけではありません。だからこそ、国際報道自由運動の箇所では『新華日報』を注で引用し(48頁)、言論統制政策の緩和の背景として検閲拒否運動や世論の動向を指摘しました(75-76頁)。また、訓政期立法院の性格付けも近年の研究成果を踏まえていますし(84頁など)、先生の研究成果も随所に引用しています(第二次憲政運動など)。なお、補足させていただきますが、ローズベルトによる民主化圧力にも触れた上で政権内部の分析をおこなっています(41頁)。
次に、政治協商会議~国民党六期二中全会~国民大会(制憲・行憲)の政治過程についてですが、「中華民国憲法」の起草・制定・施行過程に注目しただけでも、従来のような「政治協商会議を高く評価するような(その裏返しとしての国民党六期二中全会を低く評価するような)視点」からだけでは、零れ落ちてしまう事実と研究潮流が存在します。たとえば、アンドリューネイサン「中国憲法における政治的権利」(R.ランドル・エドワーズほか著『中国の人権』有信堂、1990年)は「中華民国憲法」の諸権利を比較的高く評価していますし、現代中国法研究者も同様の指摘をおこなっています(2005年6月の比較法学会・石塚迅報告など)。1990年代以降の大陸の研究書を試みに紐解いてみても、アメリカなどの圧力により民主的な憲法が求められていた事実が指摘されています。あるいは、総統の権限強化につながった「動員戡乱時期臨時条款」にしても、憲法制定直後の改憲は避けるべきだ、つまり憲政の定着に努めるべきだとの判断から、消極的に賛成した国民党員も存在します(雷震など――*のちの『自由中国』事件へ)。
第三に、蒋介石の権力の捉え方ですが、蒋介石は党・政・軍のバランサーであったが、その権力は戦後においては安定性を欠いたものであった、というのが本書の立場です(これは本書のオリジナリティーではなく、多くの研究成果に共有されています)。確かに、蒋介石個人は独裁化を志向していたのかもしません。だからこそ、孫科の自由化論を批判した(46頁)とも解釈できますし、彼は「五五憲草」に本音では共感していたのかもしれません(拙稿「国民党政権と南京・重慶『中央日報』」中央大学人文科学研究所編『民国後期中国国民党政権の研究』中央大学出版部、2005年3月)。しかし、「出版法」という具体的な政策決定過程の現場からも分かるように、「蒋介石個人=国民党の全て」であるわけではありません。
以上のような回答は、恐らく先生には納得していただけないでしょう。なぜなら、かりに先生のロジックをきちんと踏まえた上での回答であったとしても、先生との間には埋めがたい溝が残っているからです。もしそうでないとすれば、ソ連との国際関係に配慮した呉国楨の動きなどについて何らかの形で言及してくださったものと推察いたします。ですから、ここでは一つ一つにお答えすることが、「なぜ国民党という中央政府を分析するのか」という研究手法について、必ずしも生産的な対話を引き出すとは限りません。あとは、学界の先生方の御判断に委ねたいと思います。
戦勝国、国際連合、IMF、世界人権宣言、国際人権規約といった国際政治・国際経済が内政に与えた影響は極めて深刻です。こうした事実は、中央政府を分析対象とすることで、はじめて浮かびあがるものです。そしてその先に、中国史を世界史へと開き、中国各地域に根ざした国情論と地域論を展開できると考えます。旧社会主義諸国の”それぞれの”社会主義時代を近代と近代に挟まれた時代として総括しようとするのであれば(法制史研究など)、なおさらのことです。また、海外の中国研究者が宋子文を自由主義経済官僚として再考しつつあるなかで(香港中文大学鄭会欣教授など)、あるいは近現代中国の金融・経済政策をイギリス・アメリカ(1940年代後半以降においてはIMF体制)の情勢と結びつけて分析しようとする新たな研究潮流が芽生えつつあるなかで(復旦大学など)、国民政府期の憲政への道程をウィルソン主義と関連させて理解することは、20-30年後の学会動向を見据えれば、重要なはずです。そうしてこそ、改革開放から現在までの人民共和国史は言うに及ばず、1950-70年代の人民共和国史において香港・台湾を射程に入れることができます。少なくとも、1950年代の台湾政治史については、はっきりと射程に入れられます(「1940年代中国からみた『自由中国』」台湾史研究会主催「第9回現代台湾学術討論会」報告ペーパー、2005年9月3日⇒同研究会編の学会誌に掲載予定)。
ともあれ、「日本人」中国近現代史研究者としての自覚をもちつつ、そして遠くを眺めつつ、国際交流に貢献していければ、それでいいです。
若干のご指摘に関して
| ① | 1947年春から夏の情勢変化について(106頁) |
|---|---|
| コメント | 先生がここでご指摘されている事実は動かしがたい事実です。しかし、延安攻略(14頁)などの事実により「『政権内部の危機意識』はなかった」と断定することは、あくまでも推論にしか過ぎません。情勢がどうであれ、政権内部に危機感があったことは档案に記されています。 また、学生運動の高揚は先生がご指摘される「反飢餓・反内戦」運動のことですし、共産党もこの時期に地下活動を継続し(79頁の注に記した文献および135-136頁)、毛沢東も宣伝政策の強化を指示しています(78頁)。 つまり、同箇所のご指摘は、私のいう「春~夏」に含まれる事実です。「総動員法」についても、同様の文脈で触れています(87頁)。 |
| ② | 言論の自由の有無は、政府に批判的な言論・反政府的な言論の存在が許容されるか否かにある、について(107頁) |
|---|---|
| コメント | ご指摘の通りです。だからこそ、それを意図した構成になっています(21-22頁および第六章)。鈴木賢先生の書評文もご参照下されば幸いです。 |
| 補足 | あるいは『観察』の捉え方の違いに起因しているのかもしれません。 また、『周報』・『民主』の停刊処分については「言論弾圧にまつわる事件」だと評価しています(123頁)。たとえ1億のメディアが存在したとしても、言論弾圧につながる事件が一件でも発生すれば、そこには真の言論の自由はない、と私も考えます。しかし、拙著でいいたかったことは、真の言論の自由が実現していたか否かではなく、言論自由化の”方向性”についてです。その上で、政府批判の言説を取り上げています。 |
| ③ | 1948年の停刊誌について(107頁) |
|---|---|
| コメント | 第四章第四節は戦後後期の統制政策について論じているのであるから、同時期にかかわる停刊誌のみを列挙すべきだ、とのご指摘はその通りだったかもしれません。しかし、同節の最後では、1948年”まで”の情況を振り返りながら、最後の一文を記しています。その限りにおいて、事実誤認ではありません。 なお、『周報』・『民主』・『文萃』の停刊時期については、123頁・137頁で指摘しています(『文萃』の停刊時期はもしかしたら1947年6月か7月かもしれません)。 |
松田康博(防衛研究所)「書評」(『歴史学研究』No.817、2006年8月)・水羽信男(広島大学)「書評」(『史学研究』253号、2006年8月)
2006.9.21作成
松田先生と水羽先生からは、自分の今後の展望も含めて、的確なコメントをいただきました。すべて見透かされているようで怖いのですが、とても感謝しております。
ただ、それだけに、松田先生が展開されている現代台湾政治史研究にはもっと真剣に取り組まなければならない、と感じました。私は台湾研究者ではありませんが、1949年前後の大陸と台湾の関連性については、今後も何らかの形で言及していきたいと思います(2006年9月に成功大学の会議で「戦後台湾的文化論戦与殷海光―従和南京国民政府時期的文化論戦相較来看―」と題する報告をおこないました)。
また、水羽先生からいただいたご批判のうち、戦後香港史に対するやや楽観的な見通しと「文化平衡」論への理解の仕方は再考してみますが、国共両党内部の自由主義研究の必要性については、私もかねてから重視してきた点です。というのも、この研究作業は、水羽先生がご指摘されたとおり、戦後中国史像、民国政治史像をより確実に再構築するためには避けて通れない作業であり、人民共和国時代の、とくに改革開放以降の政治史、政治思想史を客観的に理解する上で「歴史的な視座」を提供してくれるからです。事例はいくつもありますが、たとえば鈴木先生が書評文でご紹介くださった武漢大学政治学系・法律系と現実政治との関係性は、民国期の政治学の導入と憲政化の歴史に規定されている側面――武漢大学政治学系の伝統――があります(校長・周コウ生の学知。なお民国の政治学については、孫宏云『中国現代政治学的展開』三聯書店、2005年に詳しいです。同書からは、「国民党系自由主義者―欧米―政治学」の関係性を読み解けます)。
いずれにせよ、1949年前後の中国政治史研究はまだまだ未開拓です。档案と新聞・雑誌・回想録をつなぎあわせていくと、まだまだ「お宝」を発見できそうです。
しかしながら、政策過程もふくめ、政治の実態を把握することは徐々に可能となっていますので、「お宝」探しをしている場合ではないかもしれません。また、アジア、世界のなかで中国政治を位置づける条件はすでに整っています。拙著がそうした研究潮流の一つの突破口になれば嬉しいです。